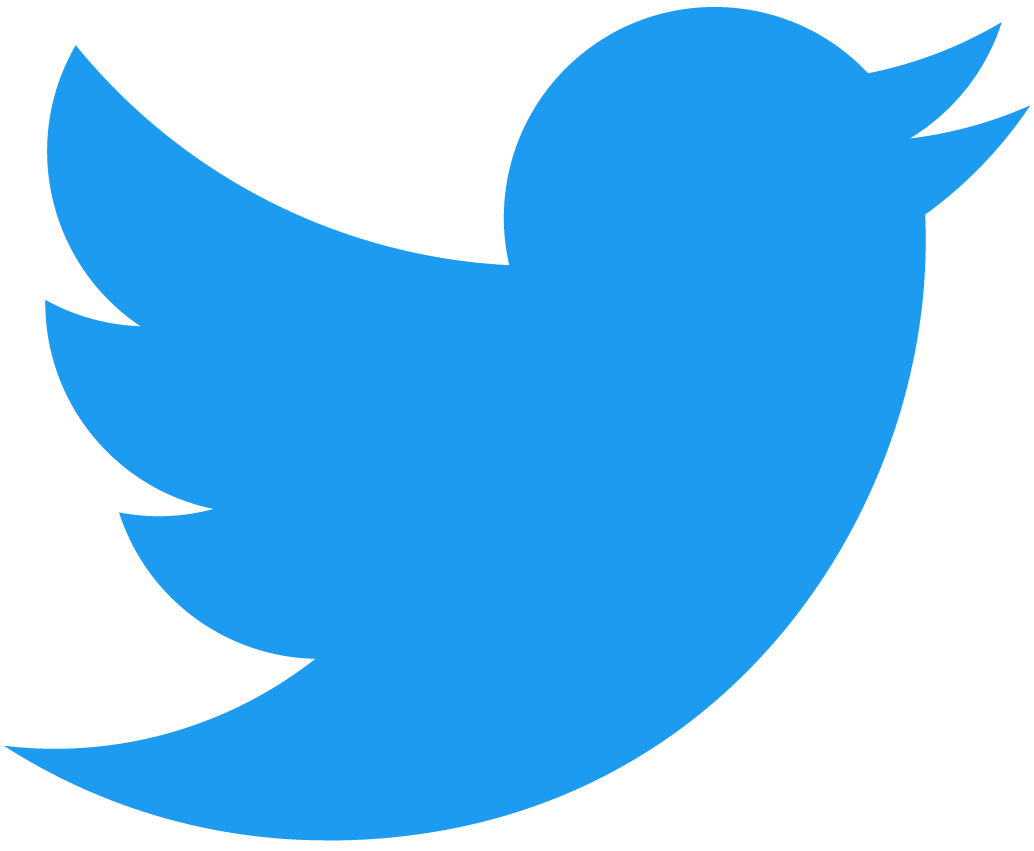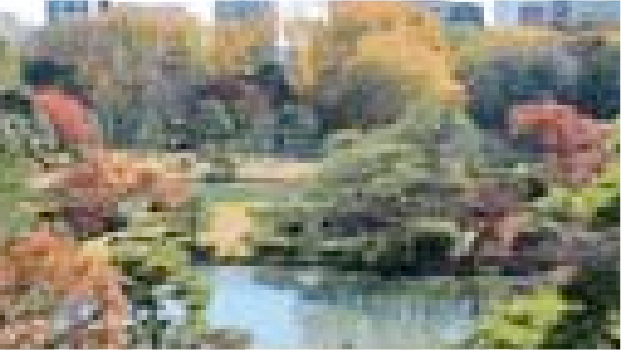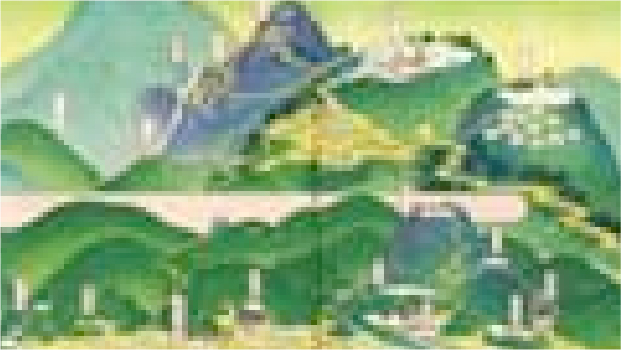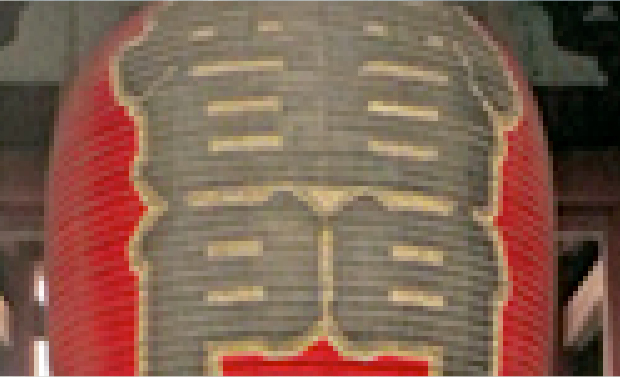八重洲を歩いてみませんか
八重洲散策コース
平成24年に、東京駅丸の内口の通称「赤レンガ駅舎」の復原工事が完了しました。「東京駅丸ノ内本屋」として国の重要文化財に指定された建物で、67 年ぶりに建設当初の壮観がよみがえりました。
その東京駅周辺には、江戸時代以来の貴重な文化財がたくさんあります。今回、八重洲北口方面を中心とした、文化財めぐりコースを御紹介いたします。
散策順路
散策コース地図


カタログ版案内(PDF)
八重洲散策コース
1 東京駅丸ノ内本屋

東京駅丸ノ内本屋
東京駅丸ノ内本屋は、日本の鉄道網の起点となる停車場の中心施設です。明治時代の計画に基づいて建設された、首都東京を象徴する貴重な建築であり、レンガを主体とする建造物としては最大規模を誇ります。
明治22 年(1889)に東海道への起点・新橋駅と東北方面への起点・上野駅を結ぶ高架線が計画され、大正3年(1914)12月に東京駅が開業しました。当初は、皇居に面した丸ノ内側だけ駅舎が建てられ、東側の八重洲口が開設されたのは昭和4年(1929)のことです。
この丸ノ内本屋は辰野金吾の設計で、南北折曲り延長約335m に及ぶ長大な建築です。中央棟の南北に両翼を長く延ばし、八角広室のドーム屋根が南北対称の位置に1 つずつ配されています。当初は3 階建てで、総建築面積10,500 ㎡と東京ドームの倍以上の規模を有していました。
空襲で大きな被害を受け、戦後の復旧は3 階部分を撤去したり、南北のドーム屋根が廃されたりするなど、規模を縮小した応急的な工事となりました。
昭和62 年の国鉄分割民営化後の再開発構想に対して赤レンガ駅舎の保存運動が起こり、平成15 年(2003) に国の重要文化財に指定されます。同19年に復原工事が始まり、戦災復旧時に縮小された3 階部分や南北のドーム屋根など、外観に関わる部分を中心に建築当初の姿へ復原されました。また、屋根材の天然スレートは産地の宮城県石巻市で補修・保管中、津波で塩害を被りました。65,000 枚中45,000 枚は使用できましたが、残りはスペイン産で補っています。
八重洲散策コース
2 北町奉行所跡

北町奉行所跡
発掘調査時の写真です
江戸の町奉行は、江戸市中の行政・司法・警察など、幅広い分野を担当していました。南北2 か所に設置され、それぞれ何度か移転しています。
北町奉行所は文化3年(1806)から幕末まで、呉服橋御門内にありました。現在の呉服橋交差点の南西、東京駅日本橋口周辺に当たります。発掘された敷地北東部の溝から角を削り面取りした石が出土し、屋敷の鬼門・艮(北東)の方角を護る呪術的な意味があるといわれています。丸の内トラストシティの東側歩道に、復元された石組みの溝と解説板が設置されています。
高橋英樹や松方弘樹が演じた「遠山の金さん」のモデル・遠山左衛門尉景元は幕末の北町奉行ですが、天保の改革に反対して僅か3 年で罷免されます。その際、町人の生活や娯楽を守ったため、「金さん」の芝居が盛んに上演され人気を博しました。後に南町奉行に返り咲き7年務めますが、南北両方の町奉行を務めるのは異例のことでした。南町奉行所跡は、現在の有楽町駅南東側です。
八重洲散策コース
3 一石橋迷子しらせ石標

一石橋迷子しらせ石標
江戸時代の日本橋~一石橋界隈は盛り場で、迷子や尋ね人が多かったようです。当時迷子は町内が責任を持つことになっており、安政4 年(1857)近隣の町名主等が世話人となり、一石橋に迷子探しの告知石碑が建立されました。
正面に「満(ま)よひ子の志(し)るべ」、左側に「たづぬる方」、右側に「志(し)らす類(る)方」と刻まれています。両側の上部に方形の窪みがあり、左側の
一石橋の北に金座支配・後藤庄三郎、南に呉服町頭取・後藤縫殿助の屋敷があり、後藤(五斗)を二つ足して一石橋の名が付いたといわれています。
八重洲散策コース
4 常盤橋門跡

常盤橋門跡(国史跡)
常盤橋門跡は寛永6年(1629)に東北の大名によって築かれた江戸城外郭門で、石垣を方形にめぐらせた「枡形門」と呼ばれる江戸城防御のための門の一つです。古くは外堀の正門であることから「追手口」、また浅草へ通じていることから「浅草口」などとも呼ばれていましたが、三代将軍家光によりこの名が付けられたといわれています。名の由来には『金葉和歌集』中の「色かへぬ松によそへて東路の常磐のはしにかかる藤波」〈巻第一〉によるという説、松の常磐(常葉)の様をかけて徳川(松平)が世の続くことを願ったという説などがあります。
この門は奥州道へと通じており、田安門(上州道)・神田橋門(芝崎口)・半蔵門(甲州道)・外桜田門(小田原口・旧東海道)などと共に江戸城と街道を結ぶ要衝として「江戸五口」に数えられます。将軍家や水戸徳川家も利用する重要な門でした。
この門自体は明治6年(1873)に廃止され、その後、石垣の一部は取り壊されますが、外郭門の中では最も残りが良い城門であるため昭和3 年に史跡指定されました。また、明治10 年(1877)にそれまでの木造橋を洋式2連の石造アーチ橋(通称 眼鏡橋)に架け替えられました。現存する東京最古の石橋です。この石造橋には「磐」の字を用いた「常磐橋」という名が付けられています。これは部首の「皿」が割れて縁起が悪いことからこの字にしたといわれています。
※東日本大震災で危険な状態となった枡形石組と石橋の復旧工事と常盤橋を明治10年の様子に戻す整備工事が行われており、現在は立ち入ることができません。ご了承ください。(平成29年度完成予定)
八重洲散策コース
5 日本銀行本店本館

日本銀行本店本館
日本銀行は明治15年(1882)に永代橋の
設計者は近代建築の巨匠であり、
本館は地上3階、地下1階。中央のドーム、付け柱などネオバロック様式の特徴が随所に見られますが、加えて厳格な左右対称、壁面などの意匠にルネッサンス様式が採り入れられています。更に水洗便所やエレベーター、防火シャッターなど当時の日本では珍しかった最先端の設備も備えていました。当初は総石造りの計画でしたが、着工翌年に岐阜県南部を中心に発生した濃尾大地震を教訓に、外壁の内側に
なお、日本銀行本店本館を上空から見ると「円」の形に見えます。当時は旧字体の「圓」を用いていたため、偶然の一致ではないかと考えられます。
八重洲散策コース
6 三井本館

三井本館
三井本館は江戸時代に三井財閥の基礎を築いた三井高利が呉服屋「越後屋」を構えた跡地に立地しています。現在の三井本館は関東大震災で被災した旧本館を建て替える形で、昭和4年(1929)に竣工しました。
設計はトローブリッジ&リヴィングストン事務所、施行はジェームズ・スチュアート社が担当。当時のアメリカの最先端の設計と技術を用いて建てられました。建築様式は19 世紀アメリカの公共建築でも数多く見られるギリシア復古調の新古典主義が採用され、建物の3面にわたり壮麗なコリント式の列柱に囲まれています。関東大震災の教訓からその2倍の地震にも耐えられる造りになっています。地下の大金庫の扉は直径2.5m、厚さ最大0.55m、重量50t もあり、運搬時はその重量から日本橋上の通行が許されず、船で新常盤橋の
かつて本館には三井合名会社、三井銀行(現三井住友銀行)、三井信託銀行(現中央三井信託銀行)、三井物産、三井鉱山(現日本コークス工業)等、の各本社が入居しており、まさしく三井財閥の本拠地としての役割を果たしていました。戦後はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)に建物の一部を接収されたことがあります。
現在、本館内には三井記念美術館があり、江戸時代以来、三井家が収集してきた貴重な美術品、約4000点が収蔵されています。
八重洲散策コース
7 三越日本橋本店

三越日本橋本店
※5階及び6階についてはオフィスフロアのため、立ち入りを制限する区域があります。また三井住友銀行の営業フロアについては、営業時間内のみ見学可能となります。建物内部の見学ガイドなど文化財の公開に係る企画はありません。
三井本館と同じく「越後屋」を起源として、その呉服屋事業を引き継ぎ、その後百貨店となります。「三越」の名は三井財閥と越後屋のそれぞれの頭文字を取ったものです。
三越本店は大正3年(1914)、三越呉服店時代に鉄筋コンクリート造りのルネッサンス様式建築として竣工し、「スエズ運河以東最大の建築」と称賛されました。その後、関東大震災で一部焼失しましたが改修増築が行われ、昭和10 年(1935)には現在の姿になりました。
正面玄関に一対の青銅製のライオン像が鎮座しています。これはロンドンのトラファルガー広場にあるライオン像をモデルにイギリスで3年の歳月をかけて鋳造されたものです。このライオン像には「必勝祈願の像」として、誰にも見られずに背にまたがると願いがかなうという言い伝えがあり、特に受験生に人気があります。北村薫が直木賞を受賞した短編小説『
建物内部はアールデコ様式の装飾が随所に見られ、吹き抜けとなっている中央ホールには三越本店の象徴的な存在となっている豪華
八重洲散策コース
8 三浦按針遺跡

三浦按針遺跡
三浦按針(ウィリアム・アダムス)はイギリス人航海士で、オランダ船リーフデ号で東洋を目指し、慶長5 年(1600)豊後国(大分県)臼杵に漂着しました。徳川家康に招かれた按針は、当時の国際情勢や造船・航海術、天文学や数学等を指導した功績で旗本に取り立てられ、相模国(神奈川県)三浦郡に領地を、江戸に屋敷を与えられました。姓の三浦は領地に由来し、按針は水先案内人です。屋敷地は現在の日本橋室町1 丁目辺りで、昭和初期まで「按針町」と呼ばれました。今でも「按針通り」が残り、「史蹟三浦按針屋敷跡」の碑があります。
按針と共にリーフデ号で漂着したヤン・ヨーステンも江戸に招かれ、屋敷地近くの「八代洲河岸」が現在の「八重洲」になりました。また、リーフデ号の積荷の大砲は、関が原の戦いや大坂の陣で活躍したそうです。
八重洲散策コース
9 日本橋

日本橋
慶長8年(1603)に初代の木造橋が架けられ、翌年五街道の起点となりました。日本橋から東隣の江戸橋にかけての日本橋川沿いには魚河岸が賑わい、橋の南北には白木屋や越後屋などの商店が建ち並ぶ、江戸随一の繁華な場所でした。また、火事の多い江戸にあって、記録に残るだけでも10回火事に遭っています。江戸東京博物館には、江戸後期の記録を基に作られた、全長28間(約51m)・幅4間2尺(約8m)の北半分14間の原寸大復元模型があり、実際に渡ることができます。
明治に入ると石造りの橋に架け替えられ、現在の橋は明治44年(1911)竣工、橋長49m、橋幅28mの石造2連アーチ橋です。橋の中央には道路の起点を示す道路元標が埋め込まれ、北西の橋詰にレプリカが展示されています。日本橋を起点とする国道は、1号(東海道)・4号(日光街道)・6号(水戸街道)・14号(千葉街道)・15号(第一京浜)・17号(中山道)・20号(甲州街道)の7つです。
北東と南東の橋詰には、工事について記した銘板があります。橋柱の川に面したところにあり、身を乗り出さないと覗けませんので御注意ください。
八重洲散策コース
10 名水白木屋の井戸

名水白木屋の井戸
日本橋の南側にあった白木屋は近江商人大村彦太郎の創業で、日本橋北側の越後屋と並ぶ呉服の大店でした。2代目彦太郎は正徳元年(1711)、日本橋周辺の水の悩みを解消するため店内に井戸を掘ります。難工事の中、一体の観音像が出たのを機に、こんこんと清水が湧き出したと言われています。以来、周辺住民のみならず広く「白木名水」とうたわれました。越前松平家では、この水で当主の病が治ったとして、明治維新まで毎朝汲み取りに行ったそうです。
昭和7年(1932)には、日本初の高層建築物火災が発生します。和服の女性がロープで脱出する際に裾を押さえるため手を放して落下し、これを契機に女性の洋風下着が普及したといわれていますが、この話は後世の脚色のようです。
白木屋を継いだ東急百貨店日本橋店が平成11年(1999)に閉店し、白木名水は消失しました。観音像は浅草寺に安置され、「名水白木屋の井戸」の碑はCOREDO日本橋アネックス前の広場脇に移設されています。
八重洲散策コース
11 髙島屋東京店

髙島屋東京店
天保2年(1831)に京都で古着・木綿商として創業した「たかしまや」が、東京の日本橋に髙島屋東京店を開店させたのは昭和8年(1933)のことです。創建時は日本生命が建設した「日本生命館」であり、髙島屋が建物を借り受ける形を取っていました。
建築に当たっては学士会館や旧前田家本邸を設計した高橋貞太郎の案が採用されました。彼は「東洋趣味ヲ基調トスル現代建築」をコンセプトに、西欧の歴史様式に日本建築の要素を随所に取り入れました。その後、高橋の意匠を継承しつつ、近代建築の手法を用いた村野藤吾の設計による増築が約30 年間にわたり重ねられ、高橋・村野両名のデザインが見事に調和した現在の姿となりました。
日本初の全館冷暖房装置を備えた百貨店であり、当時のキャッチコピーである「東京で暑いところ、髙島屋を出たところ」は一世を風靡しました。案内係が手動で操作するエレベーターは、機械が最新式に変わっておりますが、創建時のカゴを改修しながら現在も使用し、髙島屋東京店を代表する顔の一つとなっています。
昭和25 年(1950)から4 年間、百貨店の屋上では象の高子が飼育されており、「象のいる百貨店」として人気になりました。屋上へはクレーンで上げられたそうです。高子はその後、上野動物園に寄贈されましたが、現在でも小象をモチーフにした塔屋が屋上に残っています。
文化財めぐりコース
東京都にある貴重な文化財を、
より多くの皆様に身近に感じていただくために、
文化財をめぐるコースを御紹介します。
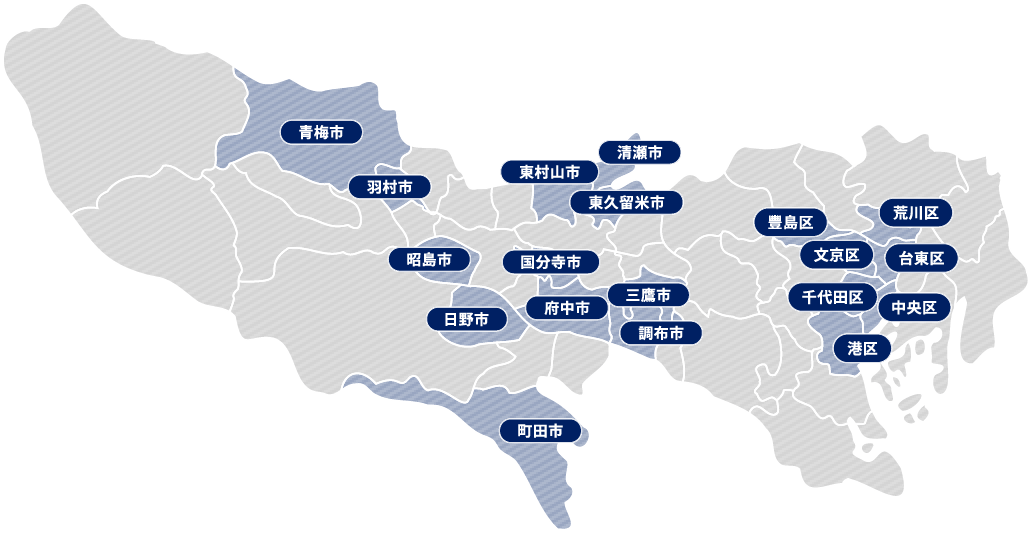
SNSシェア