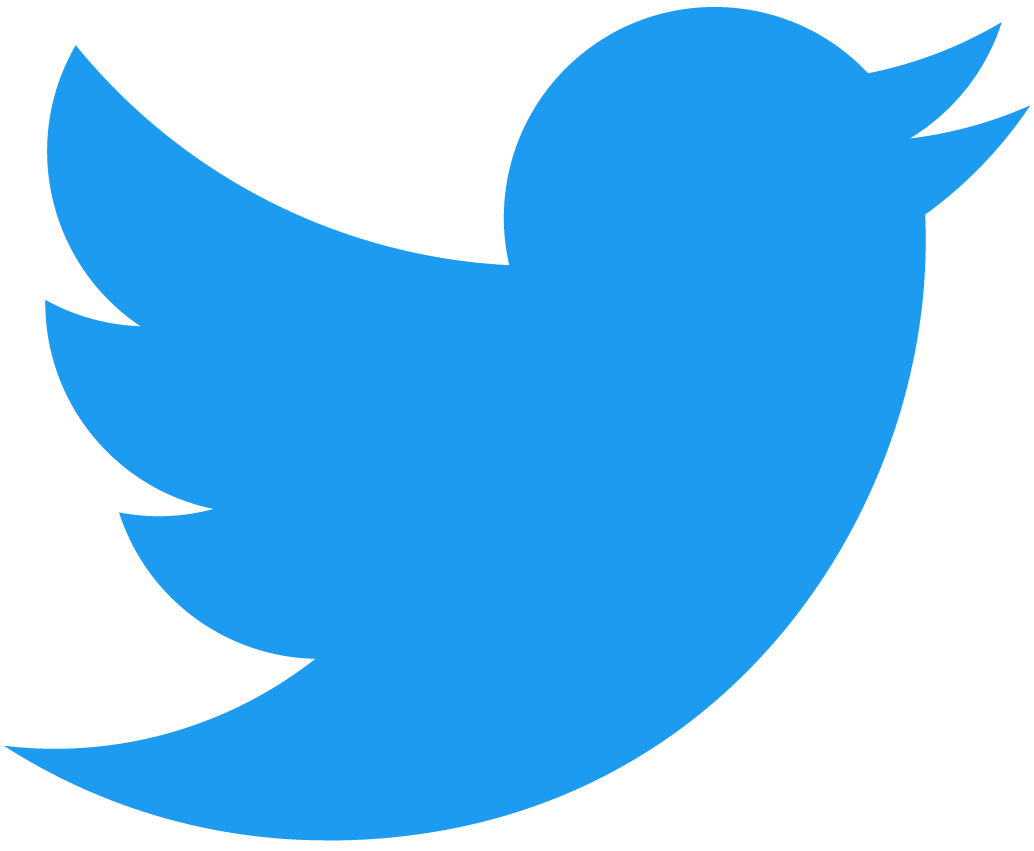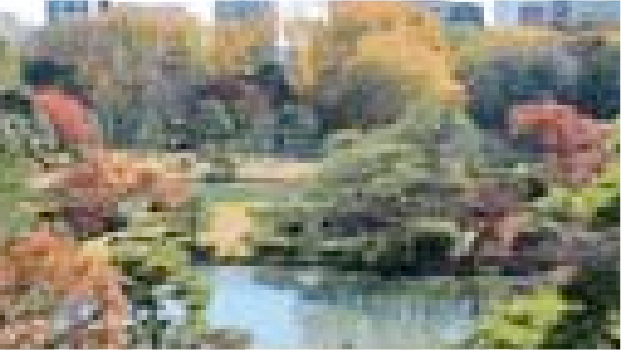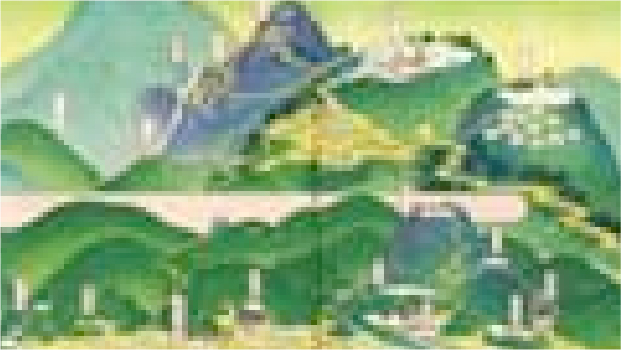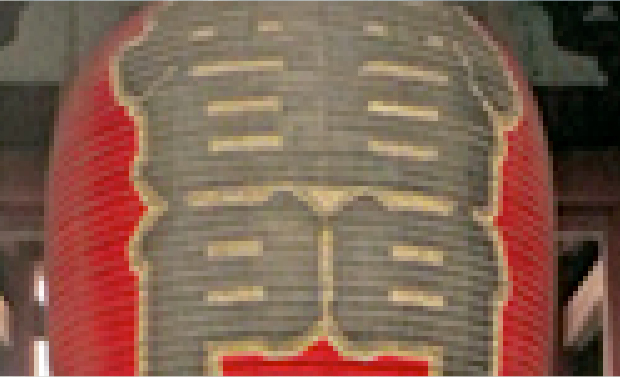旧江戸城を歩いてみませんか
皇居散策コース
東京の都心に広がる緑豊かな皇居。この地は、かつて江戸城(千代田城)と称され、徳川将軍家の居城や幕府としての政治の中心地として発展を遂げました。江戸城の外郭は、西は四谷から東は浅草まで、北は水道橋から南は虎ノ門までもありました。
今回は、この広大な江戸城のうち、一般に公開されている皇居東御苑の中の江戸城の中枢部である本丸、二の丸から皇居外苑などをめぐるコースを設定しました。また、東京国立博物館、千代田区教育委員会、東京都立中央図書館と協力し、様々な切り口で旧江戸城を紹介します。
コース案内
江戸城の成り立ちは、長禄元年(1457)の
江戸城は、本丸・二の丸・三の丸の本城、西の丸や紅葉山などの西城、広大な回遊式庭園の吹上のほか、北の丸、西の丸下など多数の堀に区切られた
散策順路
- 大手門
- 大手三の門
- 中之門
- 中雀門
- 本丸
- 天守台
- 白鳥濠の石垣と汐見坂
- 二の丸庭園
- 桜田二重櫓
- 二重橋
- 外桜田門
散策コース地図


旧江戸城を紹介する資料
カタログ版案内(PDF)
大名などの登城は、大手門と内桜田門(桔梗門)と定められていました。多数の従者を伴った大名もこの門の前で人数を限られて登城したため、多くの家臣は現在の皇居外苑周辺で待機をしなければなりませんでした。正月など一斉登城の時には、彼らを目当てに営業する商人たちが集まって賑わったといいます。
① 大手門

現在の大手門
江戸城の城門は、「
② 大手三の門
下乗門ともいい、かつては門の前に堀があって三の丸と二の丸を分けていました。古写真の右端の建物は同心番所で、現在は門内に移設されています。江戸時代は、御三家以外の大名はここで駕籠を降りなければならなかったため、「下乗」の高札が立てられていました。家臣たちはここで待っている間、他家の家臣と情報交換をしていたため、「下馬評」という言葉が生まれたといわれます。

現在の大手三の門

明治4年(1871)の大手三の門
※重要文化財 旧江戸城写真帖「本丸下乗門図」 東京国立博物館蔵
③ 中之門
大手三の門から中之門まで続く広い通路は、本丸へ向かう正面だったため、中雀門と一体となって一つの大きな
また、この区間の石垣は、大名を威圧するのに十分な巨石が使われていました。この石垣は、明暦の大火(1657)後に熊本藩細川家が瀬戸内海沿岸や紀伊半島から運んだ

現在の中之門

明治4年(1871)の百人番所
※重要文化財 旧江戸城写真帖 「本丸寺沢二重櫓図」東京国立博物館蔵
④ 中雀門
御書院門とも呼ばれ、この門を出ると本丸御殿玄関に出ます。かつては、古写真のように

現在の中雀門(今は石垣のみが残ります。)

明治4年(1871)の中雀門周辺
※重要文化財 旧江戸城写真帖「本丸書院二重櫓及重箱櫓図」東京国立博物館蔵
皇居東御苑の公開について
- 公開日 :
- 通年
(月曜・金曜(天皇誕生日以外の祝日を除く。月曜が祝日の場合は火曜が休園)・年末年始(12月28日~1月3日)・行事ややむを得ない理由のため支障のある日を除く)
- 公開時間 :
- 3月1日~4月14日・9月1日~10月末日 9:00~16:30(入園は16:00まで)
4月15日~8月末日・11月1日~2月末日 9:00~16:00(入園は15:30まで)
- 料金 :
- 無料
*皇居東御苑内の写真は、宮内庁の許可を得て撮影しています。
⑤ 本丸

手前の平面の地が本丸跡。右奥に見える富士見櫓はかつて、城内で一番富士山の眺望が良いといわれていました。
※重要文化財 旧江戸城写真帖「本丸重箱櫓、書院門渡跡、書院二重櫓図」東京国立博物館蔵
現在、芝生が広がる本丸は、多くの
御殿は南から表・奥(中奥ともいう。)・大奥の三区域から成り、その奥に天守が控えていました。表と奥には明確な境界はありませんが、奥と大奥は厳重に区画され、御鈴の廊下だけで
表は、大名などの会見の場や幕府の政庁で、御殿西側には南から、大広間、白書院、黒書院と並んでいました。これらの部屋は、様々な儀式や行事、対面の場に使われ、最も大きな大広間は将軍宣下などに使われる最も格式の高い御殿で、上段・中段・下段、入側から成り、対面する者の格によって将軍との距離と高さを違えていました。忠臣蔵の刃傷事件で有名な松の廊下は、大広間と白書院を結び、全長60mの長さは江戸城では二番目に長い廊下といわれています。
奥は、将軍の生活の場(公邸)で、御座の間(将軍の執務や生活の中心となった部屋)や御休息の間(将軍が日常生活を行う場でもあり、政務の場でもあった部屋)のほか、台所や風呂など、生活に欠かせない部屋がありました。
大奥は、御台所を中心とした奥女中生活の場(私邸)で、御広敷(御台所の居室)と長局(奥女中の住居)で構成され、表・中奥の御殿とは御鈴廊下だけで結ばれていました。14 代将軍家茂時代の記録では、400 人ほどの奥女中が居住していたといいます。ドラマでも取り上げられた江や春日の局、天障院篤姫などが居住しており、大奥を舞台にした漫画や映画も脚光を浴びました。
⑥ 天守台
江戸城天守は、慶長11 年(1606)の家康、元和8 年(1622)の秀忠、寛永15 年(1638)の家光という将軍代替わりの際に築き直された将軍権力の象徴でした。
慶長期の天守は、大天守を中心にその南東隅に
寛永期の天守は、ほぼ現在地に建てられた黒漆塗りの五層構造の建物で、高さ64mに及ぶ建物でしたが、明暦の大火(1657)によって焼失しました。翌年、加賀藩前田家が高さ約12mの
天守台の北には北詰橋門があり、この橋には北詰橋門が付いていました。北詰橋は、本陣防御のため、跳開橋となっていました。写真の北詰岩岐多聞にかかる斜めの樋は水道樋です。

現在の天守台

中央奥に見えるのが明治4年(1871)の天守台
※重要文化財 旧江戸城写真帖「天守台元奥手元蔵内面図」東京国立博物館蔵

現在の北詰渡門

明治期の北詰岩岐多聞(右)と北詰渡門(左)
※重要文化財 旧江戸城写真帖「本丸北詰渡門内水道図」東京国立博物館蔵
⑦ 白鳥濠の石垣と汐見坂
江戸城本丸と二の丸の段差は、約10m以上に及び、その段差に堀を設けて本丸を守っており、梅林坂門と汐見坂門を設けていました。汐見坂では坂上から海を臨むことができたのでこの名が付けられたといわれます。
元々本丸は堀が取り囲んでいましたが、本丸東側で現存しているのは白鳥濠のみで、一般公開されている範囲で家康時代の石垣が見られる唯一の場所です。この石垣は、乱積み・打ち込みハギという古い技法で造られ、石垣の角部は緩やかな勾配を持ち、古い形態の算木積みとなっています。
汐見坂と梅林坂に挟まれた石垣は明暦の大火後に本丸拡張のために築かれたもので、本丸付近では比較的新しい石垣になります。この石垣は、表面が正方形の石材を規則正しく積んだ切り込みハギ、布積みという積み方です。ここは、石垣の積み方を見比べやすい場所ですので、是非比較してみてください。

現在の汐見坂

明治4 年(1871)の汐見坂
※重要文化財 旧江戸城写真帖「本丸塩見櫓跡図」東京国立博物館蔵
皇居東御苑の公開について
- 公開日 :
- 通年(ただし、下記に掲げる日は休園)
(1)月曜日・金曜日(月曜が祝日の場合は火曜が休園)
(2)天皇誕生日
(3)年末年始(12月28日~1月3日)
(4)行事の実施、その他やむを得ない理由のため支障のある日
- 公開時間 :
- 3月1日~4月14日・9月1日~10月末日 9:00~16:30(入園は16:00まで)
4月15日~8月末日・11月1日~2月末日 9:00~16:00(入園は15:30まで)
- 料金 :
- 無料
*皇居東御苑内の写真は、宮内庁の許可を得て撮影しています。
⑧ 二の丸庭園
江戸城二の丸と三の丸は、将軍世子や大御所(隠居した前将軍)などが居住する御殿があり、寛永13 年(1636)に完成した御殿には、小堀遠州作といわれる庭園がありました。慶応3 年(1867)に二の丸御殿が焼失した後荒廃していましたが、昭和35 年(1960)の閣議決定で皇居東地区の旧江戸城本丸、二の丸及び三の丸の一部を皇居付属庭園として整備することとなり、昭和43 年(1968)に現在の庭園が造られ、一般公開されました。この庭園は、9 代将軍家重時代の庭絵図面を基に回遊式庭園として復原されました。現在は各都道府県の木など様々な植物が多数植えられ、訪れる人の目を楽しませてくれます。

現在の二の丸庭園

明治4年(1871)の二の丸池
※重要文化財 旧江戸城写真帖「二丸池図」東京国立博物館蔵
⑨ 桜田二重櫓

現在の桜田二重櫓
皇居東御苑の公開について
- 公開日 :
- 通年(ただし、下記に掲げる日は休園)
(1)月曜日・金曜日(月曜が祝日の場合は火曜が休園)
(2)天皇誕生日
(3)年末年始(12月28日~1月3日)
(4)行事の実施、その他やむを得ない理由のため支障のある日
- 公開時間 :
- 3月1日~4月14日・9月1日~10月末日 9:00~16:30(入園は16:00まで)
4月15日~8月末日・11月1日~2月末日 9:00~16:00(入園は15:30まで)
- 料金 :
- 無料
*皇居東御苑内の写真は、宮内庁の許可を得て撮影しています。
⑩ 二重橋

現在の二重橋
皇居外苑から皇居正門である二重橋を臨む風景は、東京観光の名所として有名です。二重橋というと皇居外苑と皇居を結ぶ石橋と思われがちですが、その奥にある橋が二重橋です。
この地点は、江戸城西の丸に位置し、手前の橋が西の丸大手門、奥の橋が西の丸下乗門に位置します。二重橋の由来は、堀が渓谷のように深く、奥の橋桁が上下二重構造となっていたために、この名が付けられたのですが、いつからか手前の石橋と奥に見える鉄橋が二重に見えることから、これらを総称して呼ぶようになりました。
現在の石橋は明治20 年(1887)、奥の鉄橋は明治21 年(1888)に架け替えられています。
⑪ 外桜田門

現在の外桜田門
この門は、古くは小田原口といい、この地域に古東海道が通っていたことをうかがわせます。そのため、ここが江戸城防備上重要な拠点となり、かなりの規模の門となったと考えられます。この門は、寛永期に建設されたようですが、現在の門は寛文3 年(1663)に再建されたものが基となっています。その後、明治4 年(1871)に一度撤去された後に再建され、関東大震災後に復原されて現在に至ります。
江戸時代には、この門を外桜田門、桔梗門を内桜田門と称し、大名登城路に利用されていました。また、幕末に桜田門外の変で井伊直弼が水戸浪士に暗殺された場所は現在の警視庁の前辺りでした。外桜田門のすぐ目の前に警視庁はあるので、ドラマなどでよく「桜田門」と称されます。
なお、田安門には「寛永十三」(1636)、清水門には「万治元歳」(1658)と高麗門の肘壺金具に刻まれており、外桜田門とともに江戸時代初期の城門を示す建造物として残されています。
皇居東御苑の公開について
- 公開日 :
- 通年(ただし、下記に掲げる日は休園)
(1)月曜日・金曜日(月曜が祝日の場合は火曜が休園)
(2)天皇誕生日
(3)年末年始(12月28日~1月3日)
(4)行事の実施、その他やむを得ない理由のため支障のある日
- 公開時間 :
- 3月1日~4月14日・9月1日~10月末日 9:00~16:30(入園は16:00まで)
4月15日~8月末日・11月1日~2月末日 9:00~16:00(入園は15:30まで)
- 料金 :
- 無料
*皇居東御苑内の写真は、宮内庁の許可を得て撮影しています。
皇居散策コース
写された江戸城 ―重要文化財「旧江戸城写真帖」―

「旧江戸城写真帖」東京国立博物館蔵



江戸城本丸跡(「旧江戸城写真帖」東京国立博物館蔵より)
東京国立博物館に収蔵されている「旧江戸城写真帖」。これは明治初頭の江戸城の姿を、いち早く写真という西洋文明の利器を用いて記録したものとして広く知られ、国の重要文化財にも指定されています。撮影された時期は明治4 年(1871)3 月。この写真帖(アルバム)には64 枚の写真が収録され、また撮影地点を理解するため江戸城の内郭・外郭の略図が二枚備わっています。
「旧江戸城写真帖」を語る時、欠かすことのできない3人がいます。まず撮影を企画した
「旧江戸城写真帖」は、蜷川の指揮の下、松三郎が撮影した写真に由一が着色したものです。用いた絵具は水彩絵具ですが、由一が目指した写実の精神が発揮されています。蜷川、松三郎、由一、いずれが欠けてもこの写真帖は成立しませんでした。
さて蜷川は、どうして明治4 年の江戸城を記録として残そうとしたのでしょうか。蜷川は写真帖にその意図を次のように書き添えています。「天下ノ勢、昔日ト相反シ、城・櫓・塹溝ハ守攻ノ利易ニ関セサル者ノ如ク相成、追々御取繕モ無益ニ属シ候様有之、因テ破壊ニ不相至内、写真ニテ其形況ヲ留置度」。つまり、戊辰戦争を経て日本が新政府によって統一された今、城郭が持っていた軍事拠点としての役割は終わり、それを維持・修繕する必要もなくなった。すると当然それらの建造物は撤去されることになり、その前に写真で記録したいとするものでした。
蜷川は続けて次のように言います。「是ハ後世ニ至リ亦博覧ノ一種ニモ相成、制度ノ沿革時勢ノ流移モ随テ可被相認儀ニ付」と。既に軍事的意義を失った城郭であるが、これを記録することは後世のために歴史の証人となるだろうと。蜷川にとって、城郭は文明開化の世で失われていくであろう多くの古いものと同列でした。そしてそのことを惜しみました。そのため、できる限り正確に伝えることにこだわり抜いたのでした。
この写真帖は本丸跡から始まって、天守跡、二の丸、三の丸、西の丸、紅葉山といった城内、そして内郭・外郭の諸門(見附)を丹念にたどり、64 枚という制約の中で城郭の構造を理解することのできる構成となっています。中でも最も数が多いのが本丸跡で、天守跡を含めると30 枚に達します。数が多いだけでなく撮影方法にも工夫を凝らしています。本丸台所三重櫓跡付近を定点として、4 周360 度がつながるように撮影したのでした。
しかし、当時の江戸城は、明暦の大火によって失われた天守閣は当然として、文久3 年(1863)と慶応3 年(1867)の火災によって焼失した本丸と二の丸はその後再建されず、主要な城内の建物は西の丸(現在の皇居)を残すのみだったのです。
では、なぜ蜷川は建物の痕跡すらない場所をこれほど執拗に記録したのでしょうか。このことについては様々に解釈されています。焼失したとはいえ本丸跡こそ260 年の長きにわたって日本を統治した徳川幕府の中心であったから。また、その幕府に代わった新政府の許可の下に行われた撮影なので、徳川の治世の終わりを明示する必要があったから。などなどです。これらの解釈は的外れではないと思います。しかし明治4 年の江戸城を考える時、忘れてはならないことは既に天皇が住まいした皇居(当時は皇城と呼びました。)であったということです。
この写真帖につけられた名称が「旧江戸城写真帖」であるがゆえに、現代の私たちは徳川幕府の居城を記録したと思いがちですが、徳川将軍という主に代わって明治天皇が新たな城主であったという事実をおいてみると、この写真帖に新たな解釈が加わるかもしれません。
皇居散策コース
江戸東京の中心に位置する常盤橋門跡

現在の常盤橋跡に架かる常磐橋(現在修理中)

※重要文化財 旧江戸城写真帖「常盤橋門」東京国立博物館蔵
近世最大級の城郭を誇る江戸城は、雉子橋門から時計回りに神田川に至る約14 ㎞の外堀がありました。このうち常盤橋門は、江戸城外郭の正門に当たり、良好に石垣が残る城門跡です。
門の創設は慶長年間に遡り、現在見られる枡形石垣は寛永6 年(1629)に奥羽の大名によって築かれたものです。「江戸城外郭御門絵図」によれば、高麗門と渡櫓門を配置する枡形門で、門の前には木橋が架かっていました。2/3 の石垣が現存し、石橋修復工事により、その内部から3本一組の木杭による橋脚と橋台石垣が発見されました。
明治時代の初め、東京の近代化の象徴として、城門に架かる木橋を石橋に架け替えられていきました。その中で明治10 年(1877)に小石川門の石垣石材を使って、二連アーチ石橋の常磐橋が架けられました。その特徴は、当時は珍しい歩車道分離で、白い大理石の親柱や花崗岩による路面、洒落たデザインの高欄手摺柵など、文明開化の面影を残した橋でした。架橋当時から錦絵や絵葉書などに登場する東京の名所となっていました。
現在も、常盤橋門跡周辺は、日本銀行本店本館など近代の文化財とともに、江戸・東京の中心地として推移した地域を示しています。千代田区では東日本大震災による解体修理を行っており、様々な資料をもとに常盤橋門の形や創建当時の石橋の面影を取り戻す工事を行っています。

旧江戸城の地形図
皇居散策コース
日比谷図書文化館常設展示

汐見多聞櫓台石垣出土 三葉葵鬼瓦

汐見多聞櫓台石垣 出土花瓶
日比谷図書文化館は皇居に近い日比谷公園に位置し、江戸・東京の歴史・文化を学習する「知の拠点」として平成23 年度に開館しました。日比谷図書文化館は、これまで区立四番町歴史民俗資料館が所蔵する資料を移転し、各種展示会や講座を開催するとともに、区内文化財保護の拠点として活動を行っています。
1階の常設展示室は、「江戸・東京の成立と展開」を総合テーマにこれまで千代田区が解明してきた郷土の歴史を伝えています。このうち、江戸城関係の展示は、「将軍の城づくり」と題して考古資料の展示のほか映像、タブレットによる検索を用いて区の歴史を紹介しています。
千代田区がこれまで実施した江戸城内や江戸城外堀跡、常盤橋門跡などの江戸城外郭の発掘調査により江戸城築城過程が明らかとなってきました。
展示では天下人による築城や城下町建設の実態について考古資料を基に紹介しています。
明暦の大火(1657)で焼けた本丸御殿に葺かれた三葉葵鬼瓦や御殿で保管されていたと思われる中国陶磁など、本丸御殿の様子も垣間見ることができます。
また、国立歴史民俗博物館所蔵「江戸図屏風」(複製)から初期の江戸城内や丸の内の武家屋敷には軒を金箔で飾られた屋敷が建ち並んでいたことを紹介します。
千代田区は、かつて江戸城を中心に主要な武家地・町人地が配置され、天下の府として日本の政治・文化・経済の中心地であり、東京となってからも、首都の中心として発展してきました。そのため、今でも区内には近世・近代の文化遺産も数多く残されています。
当館は、「千代田まちあるきマップ」とともに多くの文化遺産を学び親しむ場となり、地域を知る機会を提供することを目的としています。

日比谷図書文化館常設展示室
皇居散策コース
甲良家の図面で江戸城を歩く
東京都立中央図書館特別文庫室では、代々江戸幕府作事方の大棟梁(大工の棟梁を束ねる役職)の役職にあった甲良家に伝わる資料を多数所蔵しています。そのうち、「江戸城造営関係資料」646 点は、国の重要文化財に指定されています。
江戸幕府の作事方とは、江戸幕府の建築部門を司る役所で、江戸城に関しては本丸と西丸の表と中奥、つまり大奥との境までの建築を担当する部署でした。そのため、都立中央図書館で所蔵する造営関係資料も、江戸城の中枢・本丸御殿と世継ぎや大御所が暮らす西丸御殿の表と中奥の図面が大半です。また、作図年代も、再三火災で焼失した江戸城の最後の本丸御殿となった万延元年(1860)再建の建築図面が大半を占めています。
ここでは、それら甲良家の図面の中から江戸城のイメージ作りに役立ちそうな図面を3点御紹介します。
1. 江戸御城之絵図
吹上を除く江戸城内郭のほぼ全域が描かれています。本丸・二丸・三丸の地域は今の東御苑、西丸・紅葉山の地域は今の皇居宮殿の区域に当たります。地形は当時も現在もほとんど変わっていません。地名や建物も当時のものが随所に残っていることが分かります。

江戸御城之絵図(作図年代不明)
2. 江戸城御本丸御表御中奥御大奥総絵図
本丸御殿は江戸幕府の政務が行われた場所であり、将軍が日常生活を送った場所でもある、江戸城の中枢です。図のオレンジの部分が表と中奥、ピンクの部分の辺りが大奥です。図の左から右まで、つまり本丸御殿の南北*は約500mであったといわれています。この図は明暦の大火(1657)で焼失した後に建てられた江戸城の本丸全体を描いた平面図で、明暦の大火前まであった天守閣はなく、天守台だけが描かれています。
また、この本丸御殿も、万延元年(1860)の再建直後の文久3年(1863)、またもや焼失してしまいます。もはや幕府にも再建する力はなく、その後は西丸を政庁として政務を行い、幕末を迎えることになります。

江戸城御本丸御表御中奥御大奥総絵図(万治度)
3. 江戸御城御殿守正面之絵図
江戸城に天守閣がそびえていたのは、徳川家康が慶長12 年(1607)に造営し、元和9 年(1623)に2代将軍徳川秀忠が、寛永15 年(1638)に3代将軍徳川家光がそれぞれ再建してから、明暦3 年(1657)の大火で焼け落ちるまでの僅か51 年だけでした。この図は明暦の大火で焼け落ちた後、正徳年間頃(1711-16)、新井白石を中心に4度目の造営計画が持ち上がりましたが、再建されなかった天守閣の再建案の図といわれています。外観5層、内部は穴蔵を含めて6階で、石垣を除いた部分の建物の高さは約44.8m、日本の天守閣の中では最大規模のものでした。しかし実現には至らず、幕末を迎えることになります。
「江戸城造営関係資料」は都立図書館ホームページの「TOKYO アーカイブ」で全て御覧になることができます。御活用ください。

江戸御城御殿守正面之絵図(正徳度)

江戸城跡
写真提供:千代田区教育委員会
文化財めぐりコース
東京都にある貴重な文化財を、
より多くの皆様に身近に感じていただくために、
文化財をめぐるコースを御紹介します。
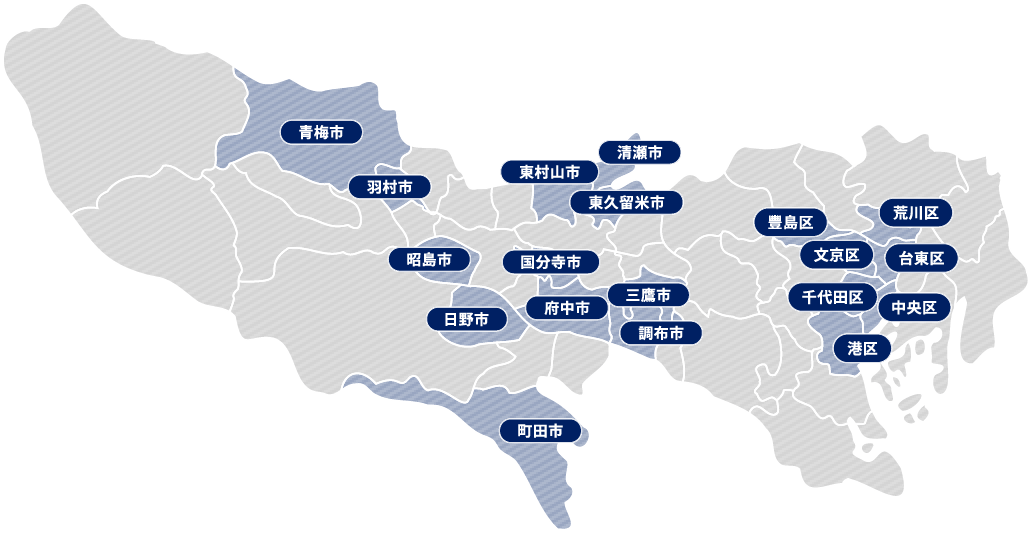
SNSシェア