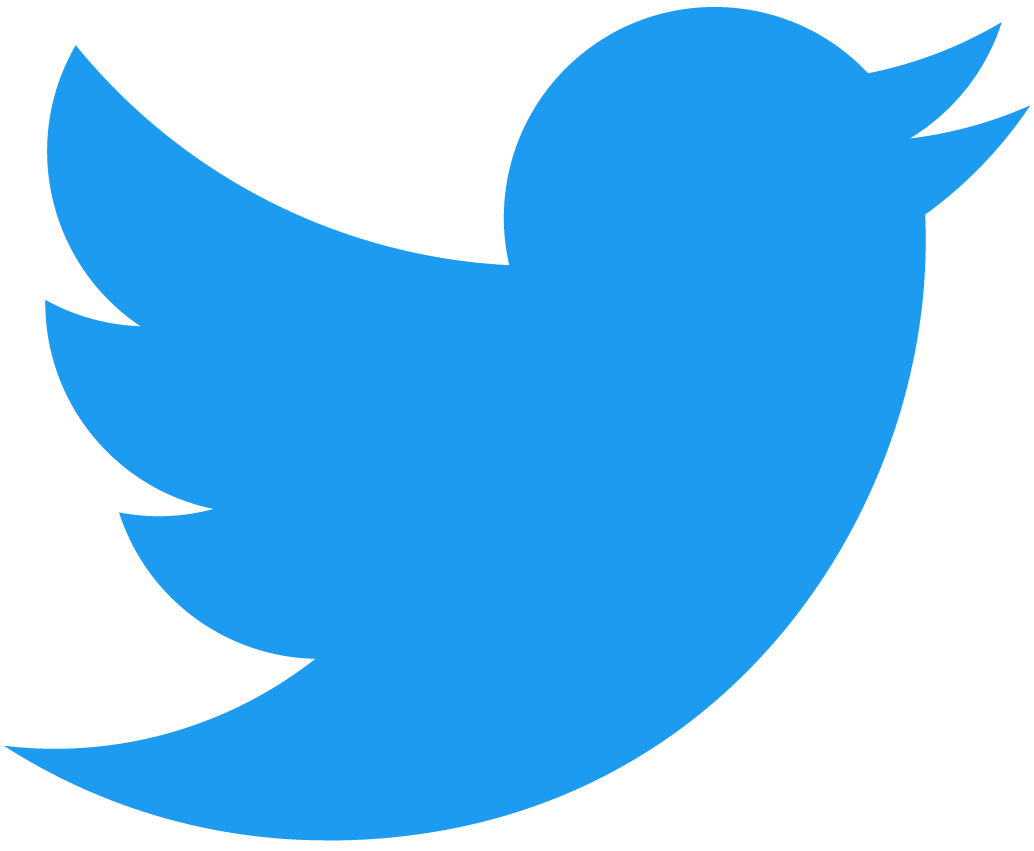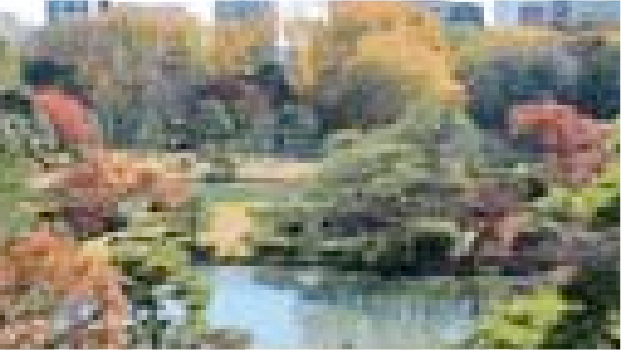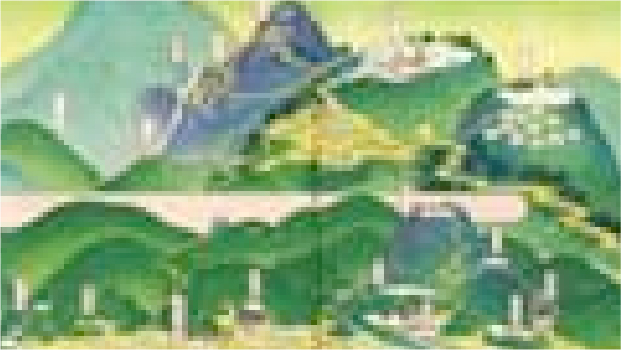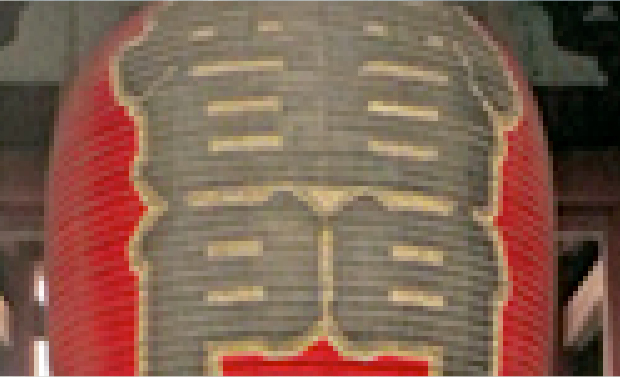
浅草を歩いてみませんか
浅草散策コース
東京観光の目玉の一つ、浅草。この地は、浅草寺の門前町を中心に発展を遂げてきました。関東大震災や太平洋戦争により、近世までの浅草の街並みはほぼなくなりましたが、焼け残った浅草寺二天門や浅草神社は文化財に指定されています。
今回は、浅草寺や浅草神社など、活気あふれる浅草の街とともに歴史を感じられる 雷門や仲見世だけではない浅草の魅力をコースを設定しました。
雷門や仲見世だけではない浅草の魅力を発見してみてください。
浅草を歩こう
『鬼平犯科帳』など池波正太郎作品にもよく登場する浅草。この「浅草」という地名が初めて文献に登場するのは、鎌倉時代に書かれた『吾妻鏡』です。養和元年(1181)、鶴岡八幡宮の造営に際して良い
江戸時代、浅草寺北西側は大名の屋敷地や畑地となる一方、雷門より南側には町屋が建ち並び、庶民信仰の寺として定着していきました。また、仲見世には茶屋が出店し、本堂西側の奥山では小屋掛けの見世物や
明治維新後、浅草寺境内は新政府により官収され、明治6年(1873)には日本最初の公園となり、浅草公園として東京市が管理することになりました。
明治23年(1890)に建設された12階建ての
しかし、江戸追慕と大正浪漫が混然一体となった近世以来の浅草の街並みは、関東大震災や東京大空襲により、ほぼ一掃されます。
昭和26年に浅草公園全域の公園指定は解除され、管理が浅草寺に戻されます。境内では、昭和33年の本堂を筆頭に、堂宇が次々と再建。娯楽施設では、戦時中閉鎖されていた浅草花やしきが昭和22年に再開、ひょうたん池(通称)埋立地には、劇場や遊技場が建設されました。
二度の大火を逃れた伝法院や二天門、浅草神社などが伝える江戸風情と、近代から続く6区の大衆娯楽文化から醸し出される雰囲気が浅草の魅力です。
散策順路
散策コース地図


コラム
カタログ版案内(PDF)
浅草散策コース
浅草寺を歩く

浅草寺本堂

浅草寺五重塔
推古36年(628)の早朝、
中世以降、源頼朝や足利尊氏などの寄進により浅草寺領は徐々に拡大していきました。江戸時代には、徳川家康により幕府の祈願所と定められ、手厚い庇護を受けます。しかし、別当(寺務を統括した職)
庶民信仰の場として定着した浅草寺は、境内に水茶屋が出店し、見世物小屋が軒を連ねるなど、江戸の名所としても広く知られるようになりました。今日、浅草観光の代名詞ともなっている仲見世は、貞享2年(1685)頃、近隣住民が境内の清掃を行う代わりに、床店を出す許可が与えられたことに始まるといわれています。
明治に入ると、雷門前には鉄道馬車が敷設され、仲見世はレンガ造りの洋風建築が立ち並び、浅草寺にも近代化の波が押し寄せました。しかし、関東大震災により近世までの街並みは失われ、東京大空襲により伝法院・二天門・浅草神社などを残し、本堂をはじめとする江戸時代以来の建物は焼失しました。
終戦から3か月後の11月には、本堂焼け跡に仮本堂(現在の淡島堂)が建てられ、地中に疎開させていた本尊が安置されました。昭和30年代に本堂、雷門、宝蔵門(かつての仁王門)が次々と再建。昭和48年(1973)には五重塔が場所を変えながらも再建され、現在に至っています。

1 浅草寺二天門

浅草寺二天門

三棟造
棟が3本あるように見えることから三棟造といわれます。
浅草寺は長い歴史の中で何度も被災し、江戸初期の寛永年間にも2度伽藍が焼失しています。そのため、寛永13年(1636)には、寺内にあった東照宮が江戸城紅葉山に遷座されました。二天門は、その東照宮随身門と伝わり、創建は元和4年(1618)ですが、現存するものは慶安2年(1649)頃の建築と考えられます。
明治初年、神仏分離令によって随身像は、仏教を守護する四天王のうち東方と南方の守護者である広目天・持国天の二天像が鶴岡八幡宮から奉納され、門の名も二天門と改称されました。
二天門は木柄が太く重厚な建物で、桁行8.13m、八脚門、切妻造、本瓦葺、
浅草寺の公開情報
- 公開日 :
- 通年
- 公開時間 :
- 終日
- 料金 :
- 無料
浅草散策コース
2 木造持国天立像・木造増長天立像

木造持国天立像

木造増長天立像
持国天と増長天は、広目天・多聞天とともに四天王に数えられます。四天王は仏教の守護神で、甲冑で武装した武将の姿に造られます。持国天は東方、増長天は南方、広目天は西方、多聞天は北方を守護するとされ、釈迦三尊などの周囲(四隅)に安置される例が多くみられます。
二天門に安置されている二天像は、昭和20年3月10日の東京大空襲の際、修理のために搬出されていた修復先にて焼失してしまい、二天門に像が無い状態がしばらく続きました。
一方、昭和31年から、上野寛永寺の厳有院霊廟勅額門の解体修理が実施されます。その中で、門の左右に付加された袖が明治期の後補部分と判明し、撤去されることになりました。このため、その袖の部分に安置されていた持国天像と増長天像は、移設を余儀なくされます。折から本堂再建に向けて境内整備を進めていた浅草寺は、像が無い二天門に安置するため、昭和32年に本像を譲り受けました。
平成19~21年に修理され、造像当時の姿に復元されています。修理の際、増長天頭部の内側に「大仏師 法橋 吉田兵部」の墨書銘が認められたことから、17世紀後半に活動していた京都七条の御用仏師・法橋吉田兵部藤房の作と分かりました。
浅草寺の公開情報
- 公開日 :
- 通年
- 公開時間 :
- 終日
- 料金 :
- 無料
浅草散策コース
3
西仏板碑

西仏板碑
写真提供:台東区教育委員会

西仏板碑
拓本写真提供:台東区教育委員会
浅草寺本堂の西側、
寛保2年(1742)8月には、暴風雨で倒壊しました。『江戸名所図会』によると3段に折れたようで、一番上の部分は伝法院の中にある稲荷社の傍らにあったとされていますが、残念ながら現存していません。その後、文化11年(1814)に10名の有志が集い、2本の側柱を建てて、支えました。
鎌倉時代末期から室町時代初期の建立と推定され、高さ217.9cm、幅46㎝、都内最大の青石塔婆です。中世の信仰を知る上で貴重な資料であるとともに、巨大板碑の典型例としても重要です。
浅草寺の公開情報
- 公開日 :
- 通年
- 公開時間 :
- 終日
- 料金 :
- 無料
浅草散策コース
4 六地蔵石燈籠

全景
写真提供:台東区教育委員会

石燈籠には六面それぞれに地蔵像が彫られています。
写真提供:台東区教育委員会
浅草寺影向堂の前に立つ石燈籠は、高さ180 ㎝余りで、六角形の火袋の各面に地蔵像が彫ってあります。しかし、現在では地蔵像も文字もほとんど風化し、火災に遭っていることもあり、判読できません。
造立年代は不明ですが、一説によると久安年間(1145~ 51)に源義朝が浅草寺を参詣した際に「
もとは雷門の東方の吾妻橋のたもとにありました。そのため、辺りの隅田川べりは「六地蔵河岸」と呼ばれていたそうです。明治23 年(1890)、道路拡幅などの区画整理に伴い現在地に移転するまで、
浅草寺の公開情報
- 公開日 :
- 通年
- 公開時間 :
- 終日
- 料金 :
- 無料
浅草散策コース
5 浅草寺六角堂

浅草寺六角堂は、『浅草寺誌』(文化10年編)に、元和4年(1618)に掘った井戸の上に建っていることを示す記述があり、さらには古い建築様式も採用されていることから浅草寺内に現存する最古の建造物と考えられます。実際、建物の底部は六角形状に廻した木製土台と基礎石で支えられ、更に、その下部に11 段の石積みをした深さ1.5m余りの井戸状の穴が堀られています。
建物は、木造、桟瓦葺、朱塗りの六角円堂で、建物中央の直径は1.82m、一面の柱間は0.91m、都内ではあまり見かけない特異な形式の建造物です。屋根を支える垂木は、建物の中心から傘の骨のように放射状に広がる「
六角堂内には、日限を定めて祈願すれば、必ず霊験があるという「日限地蔵尊」が安置されています。このため、日限地蔵堂とも言われています。
六角堂は、現在より約22mほど東方に建っていましたが、平成6年に現在の場所に移されました。現・影向堂の南基壇上に元の位置が示されています。
浅草寺の公開情報
- 公開日 :
- 通年
- 公開時間 :
- 終日
- 料金 :
- 無料
浅草散策コース
6 戸田茂睡墓

戸田茂睡は江戸時代元禄期の歌人(1629 ~ 1706)です。渡辺監物忠の六男として駿府城内で生まれました。父の死後、伯父戸田政次の養子になります。名は
墓石は、牛込萬昌院より発見され大正2年(1913)に浅草公園に移されたものです。自然石の土台、宝篋印塔の基壇、五輪塔の順にのせられています。五輪塔は茂睡自身が生前に自らの後世を供養した逆修塔です。
浅草寺の公開情報
- 公開日 :
- 通年
- 公開時間 :
- 終日
- 料金 :
- 無料
浅草散策コース
7 浅草迷子しらせ石標

浅草寺本堂の手前、向かって左側に立っている石標です。正面に「南無大慈悲観世音菩薩まよひこのしるべ」と記されており、江戸時代に迷子の情報を交換するために用いられていました。
右側面には「しらする方」と刻まれていて、預かっている迷子や訪ね人の情報を書いた紙をここに貼り付けておきます。左側面には「たずぬる方」と刻まれていて、探している迷子や尋ね人の人相や特徴などを書いた紙をここに貼り付けておきます。江戸の人々は、この張り紙を見て迷子や尋ね人を探しました。
もとは、安政2年(1855)10月2日夜10時頃に発生した安政の大地震における遊郭での死者を弔って、新吉原の楼主・松田屋嘉兵衛が安政7年3月に建てたものです。マグニチュード6.9と推定される直下型の大地震及びそれに伴う火災によって、吉原での死傷者は1000人とも言われています。
江戸時代には仁王門(現在の宝蔵門)の前にありましたが、第二次世界大戦の際に倒壊してしまい、台石の一部だけを残すのみとなってしまいました。現存する石標は、昭和32年に復元されたものです。
都内では、一石橋(中央区)にも同様の迷子しらせ石標が残されています。また、宮部みゆき『幻色江戸ごよみ』「まひごのしらべ」には浅草のものではありませんが、迷子しらせ石が登場します。
浅草寺の公開情報
- 公開日 :
- 通年
- 公開時間 :
- 終日
- 料金 :
- 無料
浅草散策コース
8 浅草神社を歩く

「三社祭」
© 台東区教育委員会所蔵 須賀コレクション

びんざさら巡行の様子

白鷺の舞 大行列の様子
浅草寺本堂の東側、石造大鳥居をくぐれば、三社祭で名高い通称「三社さま」として知られる浅草の総鎮守、浅草神社の境内です。浅草寺創設に深くかかわる檜前兄弟の網にかかった観音像を土師中知が自宅を改めた寺に
現在の浅草神社社殿は、度重なる焼失ののち、三代将軍徳川家光の寄進により慶安2年(1649)に完成したものです。浅草寺境内にあった東照宮が江戸城内に遷座されたため、東照宮に祀られていた家康像も三社権現社に合祀され、浅草寺と一体に保たれてきましたが、明治の神仏分離令により独立、浅草神社と改称しました。境内には、浅草と縁の深い新門辰五郎が、安政5年(1858)に京都の伏見稲荷より勧請した被官稲荷も残されています。
都内でも有数の祭りである三社祭は、毎年5月の17日18日に近い金曜・土曜・日曜に行われる、浅草神社の例大祭です。祭神三柱の
『浅草寺縁起』によると、正和元年(1312)の3月、「神輿をかざり奉り、船遊の祭礼をいとなみ、天下の安寧を祈り奉る」という神託があり、これが三社祭の始まりとされています。かつては観音示現の日である3月18日に行われ、丑・卯・巳・未・酉・亥の隔年に船渡御が行われました。江戸時代には、この18日にちなんだ氏子十八ヶ町が、趣向を凝らした山車の豪華さを競い合いました。
明治に入ると船渡御も山車も無くなり、日程も5月17日18日に改められました。替わって神輿の町内渡御が行われるようになり、昭和38年からは現行の日程になりました。初日の金曜には大行列が行われ、囃子や鳶木遣の音曲に導かれ、びんざさら舞や手古舞、白鷺の舞等が見番を出発して浅草の街を歩きます。土曜は約100基の町内神輿の連合渡御、日曜は3基の本社神輿(一之宮・二之宮・三之宮)が氏子44ヶ町を渡御します。
8 浅草神社

浅草神社拝殿外観

浅草神社拝殿内部
現在の浅草神社は、寛永19年(1642)に浅草寺諸堂とともに焼失したのち、慶安2年(1649)に完成しました。『浅草寺誌』によれば、神社の社殿には当時の金額で1,200両余もの巨額の建設費が当てられました。
一般的な権現造(本殿、幣殿、拝殿が一体的になった造り)とは異なり、本殿・幣殿と拝殿の間が渡廊で繋がれています。拝殿は桁行七間の横長に広い建物で、三社祭では「びんざさら舞」の奉納が行われます。本殿は三間社流造で、檜前浜成・竹成兄弟と土師中知の三人を祀ります。
社殿全体は、柱や縁廻りなど大部分を弁柄漆塗りとし、建具の黒漆塗りが全体を引き締めています。鮮やかなのは長押上部の小壁で、黄金のような黄土地に、鳳凰、麒麟、飛龍などの瑞祥を表す霊獣を極彩色で描いています。これらの漆塗りと彩色は、昭和38年の修理以来、経年劣化が目立ってきていたため、平成6~7年に修営を行いました。よみがえった色彩の鮮やかさには、眼を見張るものがあります。関東大震災や戦災による被害を免れ、360年以上を経た現在も当時の面影をそのままに残す、貴重な文化財です。
浅草神社の公開情報
- 公開日 :
- 通年(境内のみ)
- 公開時間 :
- 終日
- 料金 :
- 無料
浅草散策コース
9 浅草観音戒殺碑

写真提供:台東区教育委員会
隅田川に架かる駒形橋の辺りには船着き場があり、自動車や鉄道が無かった頃は隅田川の舟運で
駒形堂は、浅草寺の本尊・聖観世音菩薩を檜前兄弟が陸揚げした川べりに建立されました。天慶5年(942)の創建と伝えられています。
浅草寺は、徳川家康が祈願所にするなど、江戸幕府に重んじられました。元禄5年(1692)生類憐みの令で知られる五代将軍綱吉の時代に、浅草寺本尊が現れた霊地を禁漁にしました。駒形堂を中心に、南は諏訪町(台東区駒形)から北は聖天岸(同区浅草7丁目)までの十町ほどの川筋です。ちなみに十町は、およそ10ha=10万㎡で、東京ドーム2個分より少し広いくらいの範囲です。翌年、浅草寺近辺の隅田川が殺生禁断の地となったことを記念して、浅草寺第4世権僧正宣存が高さ183.5cm、正面幅61cmの戒殺碑を駒形堂の境内に建てました。
元禄期の信仰及びその周辺の状況を明らかにする貴重な資料です。
浅草観音戒殺碑の公開情報
- 公開日 :
- 通年
- 公開時間 :
- 終日
- 料金 :
- 無料
浅草散策コース
伝法院庭園

仲見世通りを宝蔵門に向かって歩くと、伝法院通りを渡ったすぐの左手、奥まったところに荘厳な表門があります。この表門をくぐると、浅草寺の本坊であり貫首の居宅でもある伝法院です。その敷地の大半を占める伝法院庭園は、観光客の喧騒から隔絶され、静穏な空気が流れる、江戸時代から継承される都内に残る数少ない寺院庭園です。
作庭は中世に遡るとも考えられますが、古図面や造園手法から、江戸時代初期には北側と西側に池を配する、現在とほぼ同じ地割であったことが分かります。
庭に面した大書院から西側の池を眺めると、左手に大きな築山があり、その山頂から流れ落ちる三段の枯滝石組と水面を表現した州浜が広がります。そのまま視線を中央に移すと、出島や中島によって起伏に富んだ護岸が展開します。
池泉を回遊して大書院の向かいにある中島に立つと、飛石を配した州浜と大書院を通して、再建された五重塔を一望できます。西側池泉の護岸とは対照的に、緩やかな線形をもつ北側池泉は両池をつなぐ渓流部にかかる石橋から望めます。
伝法院は、徳川将軍などが御成りの際に御膳所として使用したことから、大名ですら簡単に拝観できない秘庭でした。しかし、明治6年(1873)に浅草寺境内が浅草公園に指定されると、昭和5年から太平洋戦争開戦までの間、東京市により公園として一般公開され、昨今は浅草寺により、期間を限って公開する年もあります。関東大震災や太平洋戦争で江戸情緒の多くが失われた浅草において、その風情を今日に伝える庭園です。
伝法院庭園の公開情報
- 通常非公開
浅草散策コース
浅草神社のびんざさら

浅草神社のびんざさら 肩揃
びんざさらは、「拍板」「編木」などと書かれる楽器です。長さ15cm厚さ6mmの檜板を108枚連ね、両端を持ち開閉することで板を擦り合わせて音を出します。この楽器を使う舞が三社祭の初日に奉納されます。
三社祭の幕開けとなる金曜午後の大行列の中程に、赤青一対の大きな獅子頭、膝まで届く赤毛のカツラを被った大太鼓役、綾井笠で顔を隠したびんざさら役3人・摺太鼓役2人・笛役2人他、「びんざさら舞」を舞う人達が並びます。大行列が神社に到着すると、彼らだけが昇殿を許されます。拝殿にて、雌獅子舞・雄獅子舞・雌雄獅子舞(つるみ舞)の3つの獅子舞と、
『浅草寺縁起』には鎌倉末期に三社祭が始められた頃の姿が描かれていますが、この中に「びんざさら舞」の姿も見られます。中世以来の芸能を今に伝える、貴重な無形民俗文化財です。
浅草散策コース
神谷バー本館

吾妻橋の近くに関東大震災以前から建ち続ける浅草のランドマークの一つです。
明治に入ると浅草寺境内は公園化され、西側には劇場等の娯楽施設が多く建ち並びます。特に電気館(映画館)は人気で、文人など多くの客が集まりました。当時「電気」は目新しいものの象徴で、アルコール度数が45度もあった強いお酒は「デンキブラン」と名付けられました。この「デンキブラン」や「ブドー酒」は文学作品にも登場します。神谷バーの創業は明治13年(1880)で、同45年に洋風の「神谷バー」に改造し浅草で最初のバーといわれました。
現在の本館は、大正10年(1921)にいち早く、鉄筋コンクリート造で建設されたもので、正面の大きな丸窓付き三連アーチが特徴です。
神谷バー本館の公開情報
- 公開日 :
- 通年(外観のみ)
- 公開時間 :
- 終日(外観のみ)
- 料金 :
- 無料(外観のみ)
浅草散策コース
ギャラリー・エフ蔵

浅草寺雷門の南側、吾妻橋に近く隅田川に面したこの辺りは、江戸から明治にかけて材木町と呼ばれていました。実際、材木や竹の問屋が多かったそうです。
この土蔵は、竹屋という大きな材木問屋の内蔵(家財道具や大事なものをしまう)でした。かつては屋敷や店が隅田川まで建ち並んでいたことでしょう。
土蔵は柱も梁も太く、壁の左官仕事もしっかりした、非常に堅牢な造りです。2階の梁下面に「慶応四戊辰年八月吉日 三代目竹屋長四郎」の墨書があります。この年(1868)9月には明治に改元、その後の関東大震災や戦災にも耐えて、江戸の息吹を現在に伝える貴重な文化財です。現在は喫茶店併設のアートスペースになっています。
ギャラリー・エフ蔵の公開情報
- 公開日 :
- 通年(ただし、火曜及び臨時休業日を除く)
- 公開時間 :
- 11:00~18:30 (ただし、展示の種類等によって変更あり)
- 料金 :
- 無料
 カフェ
カフェ
文化財めぐりコース
東京都にある貴重な文化財を、
より多くの皆様に身近に感じていただくために、
文化財をめぐるコースを御紹介します。
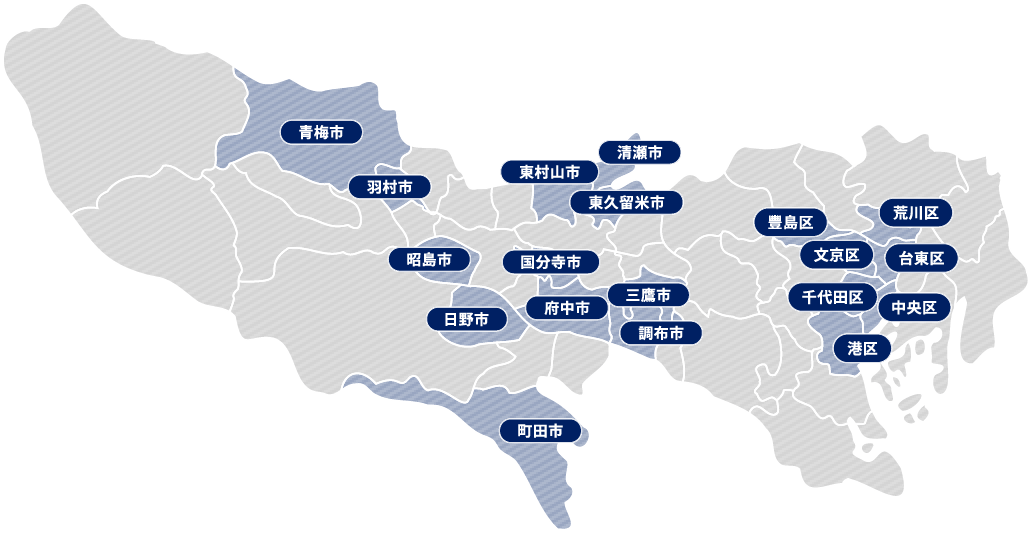
SNSシェア